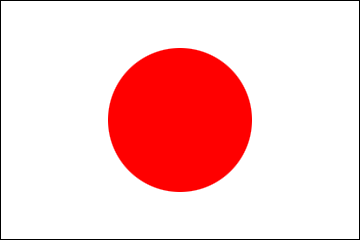在留証明
令和7年9月29日
対象
日本国籍を有しており、当館管轄地域に居住している方
必要書類
(1)共通
(ア)在留証明願(当館窓口でも入手することができます。)
在留証明願及び記入例は、以下からダウンロードすることができます。
- 在留証明願(形式1:現住所の証明)のダウンロード
- 在留証明願(形式1:現住所の証明)記入例のダウンロード
- 在留証明願(形式1:現住所の証明)(恩給・年金受給者用)記入例のダウンロード
- 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明、同居家族の証明)のダウンロード
- 在留証明願(形式2:過去の住所及び在住期間の証明)記入例のダウンロード
- 在留証明願(形式2:同居家族の証明)記入例のダウンロード
(イ)申請者の日本国籍を確認できる書類(有効な日本のパスポート等)
(ウ)米国での滞在資格を確認できる書類(米国ビザ、永住権等)
(エ)恩給・年休受給手続き用の場合は、受給を証明するもの(受給証書、現況届のはがき、裁定通知書等)
(オ)「本籍地」欄に都道府県名のみでなく、番地まで記載する必要がある場合は戸籍謄(抄)本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁
(2)形式1:現住所の証明の場合
- 現住所を確認できる書類(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等で申請者の氏名、現住所が入ったもの)
- 在住期間(いつからその住所に居住しているか)も証明する必要がある場合は、
(2) 現在も同じ住所に居住していることを立証する書類(公共料金の請求書または領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、有効な米国運転免許証、銀行のステートメント等で申請者の氏名、住所及び直近の日付が入ったもの)
(3)形式2:過去の住所及び在住期間の証明の場合
・過去の住所の居住開始年月日、申請者氏名及び住所が記載されている書類(例:米国の運転免許証、家の契約書、公共料金の明細等)
例)過去の住所が1つの場合0
過去の住所が2つ以上の場合
(4)形式2:同居家族の証明の場合
・同居家族の証明は、証明対象となる同居家族(日本国籍保有者に限る)の、
(ア)有効な日本のパスポート
(イ)米国での滞在資格
(ウ)米国での現住所を証明するもの(住所及び氏名が記載されているものが好ましい)
手数料
こちら をご覧ください。窓口での申請の場合、手数料は証明書交付の際に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェックやクレジットカード等はご利用になれませんのでご注意ください。
以下の(ア)から(ク)の公的年金受給のための申請は、法令上、手数料が免除となります。
(ア)恩給(総務大臣裁定)
(イ)執行官年金(総務大臣裁定)
(ウ)国会議員互助年金(総務大臣裁定)
(エ)戦傷病者戦没者遺族等援助法による年金(厚生労働大臣裁定)
(オ)国民年金(厚生労働大臣裁定)
(カ)厚生年金(厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済年金、全国市町村職員共済組合連合会および日本私立学園復興・共催事業団裁定)
(キ)労働者災害補償保険年金(労働基準監督署長裁定)
(ク)文化功労者年金(文部科学大臣裁定)
なお、国民年金基金・企業年金(含:「○○厚生年金基金」)につきましては、手数料免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
以下の(ア)から(ク)の公的年金受給のための申請は、法令上、手数料が免除となります。
(ア)恩給(総務大臣裁定)
(イ)執行官年金(総務大臣裁定)
(ウ)国会議員互助年金(総務大臣裁定)
(エ)戦傷病者戦没者遺族等援助法による年金(厚生労働大臣裁定)
(オ)国民年金(厚生労働大臣裁定)
(カ)厚生年金(厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済年金、全国市町村職員共済組合連合会および日本私立学園復興・共催事業団裁定)
(キ)労働者災害補償保険年金(労働基準監督署長裁定)
(ク)文化功労者年金(文部科学大臣裁定)
なお、国民年金基金・企業年金(含:「○○厚生年金基金」)につきましては、手数料免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
注意事項
○在留証明願の「本籍地」「この場所に住所(または居所)を定めた年月日」の記入ぶりは提出先によって異なる場合があります。当館へ申請される前に、必ずご自身で提出先へご確認ください。
○在留証明願には、証明書の提出理由及び提出先の記入が必須となります。必ず事前にご確認ください。
○原則代理申請は認められていません。申請者本人が直接当館領事窓口にお越しいただく必要がございます。
なお、当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。
○証明書に記載される「(証明する住所に)住所を定めた年月日」は、必要書類(3)でご提示いただく書類が基となります。
例1)提出書類が家屋の賃貸・売買契約書の場合、同契約書に記載されている入居年月日からの在留を証明することになります。
例2)提出書類が米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月日からの在留を証明することになります。
○次の要件をすべて満たす方は、遠隔地にお住まいでない場合も郵便での申請が可能です。
(1)申請手数料が免除となる恩給、年金または特別給付金(「手数料」参照)の受給手続きのために申請される方
(2)過去に当館で上記目的のために在留証明を取得した方で、その時点から現住所に変更がない方
○在留証明は、申請時に当館管轄地域に居住していることが発給条件となります。帰国した後や、他公館管轄地域に転居した場合は、当館では在留証明を発行することができません。
○在留証明願には、証明書の提出理由及び提出先の記入が必須となります。必ず事前にご確認ください。
○原則代理申請は認められていません。申請者本人が直接当館領事窓口にお越しいただく必要がございます。
なお、当館では遠隔地にお住まいの方に対して、郵便による申請受付及び交付を行っております。詳しくはこちらをご確認ください。
○証明書に記載される「(証明する住所に)住所を定めた年月日」は、必要書類(3)でご提示いただく書類が基となります。
例1)提出書類が家屋の賃貸・売買契約書の場合、同契約書に記載されている入居年月日からの在留を証明することになります。
例2)提出書類が米国運転免許証の場合、同免許証に記載の発行年月日からの在留を証明することになります。
○次の要件をすべて満たす方は、遠隔地にお住まいでない場合も郵便での申請が可能です。
(1)申請手数料が免除となる恩給、年金または特別給付金(「手数料」参照)の受給手続きのために申請される方
(2)過去に当館で上記目的のために在留証明を取得した方で、その時点から現住所に変更がない方
○在留証明は、申請時に当館管轄地域に居住していることが発給条件となります。帰国した後や、他公館管轄地域に転居した場合は、当館では在留証明を発行することができません。
オンライン申請について
在留証明は、オンラインで申請及び交付が可能となっています。詳しくはこちらをご確認ください。
また、在外公館が発行する在留証明以外にも、海外に居住していたことを証明する書類(例:海外の運転免許証、公共料金領収書、親の勤務先が発行した海外勤務証明書、米国現地学校が発行した在学証明書、日本の法務省が発行する出入国記録に係る証明書、日本の市役所等が発行する戸籍の附票、パスポートの出入国スタンプ等)があり、一部学校ではこのような書類を受け付けておりますので、既にご帰国されている方は、受験予定の学校へ直接ご確認ください。
帰国後に海外子女枠で日本の学校を受験予定の方へ
帰国した後に、お子様が海外子女枠等で日本国内の学校を受験する際、過去に海外に居住していたことを証明するよう、学校側から求められることがあります。日本へ帰国後、前述のような枠での受験を予定されている方は、事前に学校側に必要書類を確認の上、海外での居住有無を証明する必要がある場合には、ご帰国前に在留証明書を取得されることをお勧めします。また、在外公館が発行する在留証明以外にも、海外に居住していたことを証明する書類(例:海外の運転免許証、公共料金領収書、親の勤務先が発行した海外勤務証明書、米国現地学校が発行した在学証明書、日本の法務省が発行する出入国記録に係る証明書、日本の市役所等が発行する戸籍の附票、パスポートの出入国スタンプ等)があり、一部学校ではこのような書類を受け付けておりますので、既にご帰国されている方は、受験予定の学校へ直接ご確認ください。